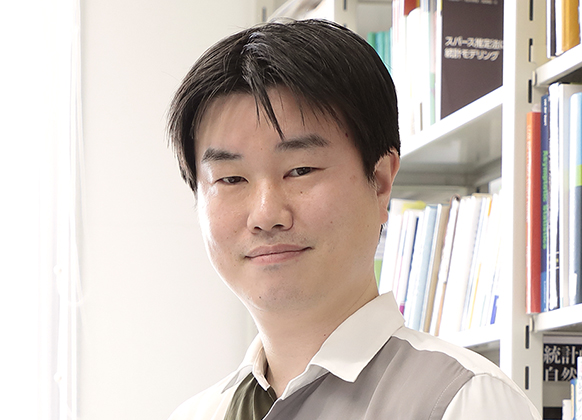教員インタビュー
目の前のことをがむしゃらに取り組んでいたらいつの間にか統計学の研究者になっていました。人生、行き当たりばったりでも何とかなります!
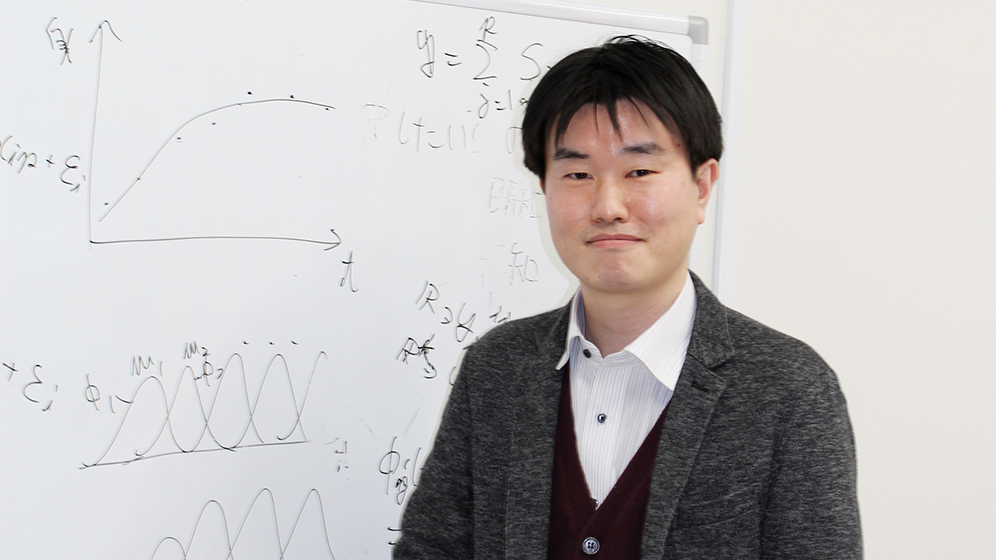
松井 秀俊
データサイエンス学部 教授
研究分野:統計的モデリング
計測機器が発達し、大規模なデータが増えてきています。松井秀俊准教授はこのようなデータを分析するための方法である関数データ解析とスパース推定の2つの研究を行っています。以前は企業で働いていましたが、現在は研究者をしているという経験豊富な先生です。一方で、かわいくてシュールなゆるキャラが好きで研究室に飾っているという一面もある松井先生に、企業から研究職まで、幅広く語ってもらいました。
聞き手 データサイエンス学部1期生/3年(当時) 藤山 南々子
※本記事は、滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センターのセンター誌『Data Science View Vol.3』の特集企画『私の「研究」履歴書』に掲載された記事の内容に若干の修正を加えたものです。本文中に記載されている内容や所属・肩書き等はすべて取材当時のものです。
「数学」、中でも「統計学」で人の役に立てる!
Q.どうして統計学を学ぼうと思ったのですか?
意外かもしれないけど、小学1年生の時に、数を数えるだけの問題を間違えてすごく恥ずかしい思いをしたことを覚えています(笑)。それから、近所の公文式に小学2年生から高校3年生まで通って…いつのまにか数学が好きになって、今に至ります。あ、あと高校生の時「アクチュアリー」といった保険数理の仕事を知って、これまで学問分野の一つとしか見てなかった数学でちゃんと人の役に立てるんだと知ったことが大きいですね。統計学を学ぼうと思ったのは、大学2年生の前期で初めて統計学の授業を受けて、そこで、製薬企業で統計的仮説検定を使って薬が効いているかどうかを検査するという話を聞いて、数学の中でも人の役に立てる仕事が多いのは統計学だと思ったからですね。
Q.どうして就職をしたのですか。また研究者になろうと思ったきっかけも教えてください。
普通の流れだったら大学にずっと残って研究者なんだけど、なんとなーく企業も経験しておきたいなというのが動機ですね(笑)。研究者になろうと思ったきっかけは、漠然といずれはアカデミックなことしたいなとは思っていて、その矢先に元いた大学の助教の公募の話が来たことです。これはほんとに運とタイミング。自分の人生を語るうえで「なんとなく」と「行き当たりばったり」はキーワードなのかもしれないな(笑)。
Q.企業にいたころと今(研究者)とで大きな違いは何ですか。
研究者になったことでたくさん経験ができるっていうのはあるかな。研究者や企業の方の前で講演するだけじゃなくて、放送大学でテレビに出たりもしたし(笑)。その点で言うと企業でやる内容はあまり公では話せないけど、研究者は逆にオープンといった違いがある感じ。
データに恵まれている環境で研究を進める!
Q.先生の研究テーマは「関数データ解析」と「スパース推定」ですが、どのようなことをしているのでしょうか。
関数データ解析では経時測定データをどういう風にモデリングしてうまく分析できるかを研究しています。わかりやすい例でいうと気温のデータですね。月別の平均気温データは1年間で12個の点として観測されますが、本来は滑らかな曲線が描けるはずの情報なので、点ではなく線としてデータを扱ってやりましょう、っていうのが関数データ解析の基本的な概念。で、もう一つやっているスパース推定は、目的変数に大いに影響している変数の選択を少ない計算コストでできるものです。これは関数データのモデリングに融合させることもできます。共同研究で遺伝子のデータや植物のデータを解析しました。今はトマトの収穫量と、気温などの栽培環境との関係をモデル化するための研究をしています。
自力でデータサイエンスを広げていくべき
Q.これからデータサイエンティストになる方々に一言メッセージをお願いします。
今、データサイエンスがブームになっているわけですがいずれこのブームは去ると思います(笑)。去るんだけど、じゃあそれでデータサイエンスへの需要がなくなるかと言われると必ずしもそうではないはずです。なので自分たちでデータサイエンスを活かせる場所を見つけて、需要を広めていってほしいなと思います。